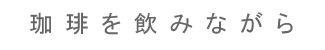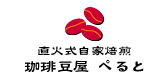



久々の更新、久々の登山。
今回は山梨県の山、笠取山(1953m)に行ってきた。山梨県の山ではあるが埼玉県との県境に頂上がある。西に甲武信ヶ岳、東には飛竜山から雲取山へと尾根がつながっている。
登山口までは遠いが比較的アップダウンが少なく、好展望なので初心者向けの山だ。
新座市の自宅から車で約3時間。奥多摩湖まで2時間。そこからカーブだらけの青梅街道を1時間近く走る。すれ違う車がほとんどなくなってきた頃、一之瀬林道に入るわき道から登山口に入っていく。 ちなみにこの一之瀬林道に入るところは「オイラン淵」で有名なホラースポットである。口封じのために55人の遊女が谷底へ突き落とされた悲しい場所だ。→オイラン淵
実はこの笠取山は今年の7月に登山口まで行ったにもかかわらず、登らずに帰ってきた山だ。というのも、いざ登ろうとした時に上着を忘れたのに気付き、これじゃ頂上は寒いだろうしフリースはあるけど大げさだろう、と悩み、ちょうど沖縄に大型台風が近づいていて晴れてはいるものの天候は不安定だった。上空を見ると雲が速く流れていたのでしばらく悩んだあげく中止したのだった。
ええ、根性なしです。
今回は、しっかり準備して、少し眠いけど天気もばっちり、昨年の鷹ノ巣山以来9ヶ月ぶりの登山。上着もちゃんと持った。
作場平という所から登っていく。峠に出るまではヤブ沢というルートを登る。その名のとおり、クマザサが生い茂った登山道を沢沿いに登っていく。
こんなところ。クマザサが多いので熊よけの鈴をストックに付けた。

こういう橋がいくつもかけてある。道標やベンチなど登山道はよく整備されている。

緩やかな登りが暫く続いたと思ったら1時間もしないうちにヤブ沢峠という分岐点に出る。
そこからは更に整備された登山道を行く。これまた緩やかな登り。
広葉樹いろいろ。

大して歩かぬうちに笠取小屋に着く。素泊まり用の小屋だそうだ。ちなみにここのトイレはバイオトイレが導入してある。オガクズなどと混ぜて微生物に分解させる。
しばし休憩。

緩やかな登りではあるが、シャツは汗でびっしょりだ。ザックのショルダー部分も汗でぬれている。
気温は22度だった。風は爽やかで気持ちがよい。
再び歩き始めると、だんだんと草原がまばらに見えてきて、すぐに分水嶺がある小さな丘に立つ。
この小さな丘に落ちた雨が、流れる方向によって多摩川、荒川、富士川のいづれかになる。(左下の白いのが分水嶺の印、奥の山が本日の笠取山)

分水嶺をあとにして進むにつれ奥秩父の高原風景が気持ちよい。

本日の山、笠取山の登山道。頂上まで急登だ。写真ではよくわからないが、この写真の場所から一度下ってから登りが始まる。

一番下がったところから見上げる。

ゆっくり登ればしんどくは無い。勾配がきついのでカメラを置く場所も確保できず、構図もうまくとれず、とった後またカメラのところまで戻るのが面倒なのでこんな写真しか取れなかった。

頂上。右奥に富士山。

左下の木の無いところが分水嶺から通ってきた道。

山々の名前はわからないけど、東側の景色と空。

頂上は風がとても強く、汗をかいたTシャツが冷えて寒いので急いで忘れなかったシャツを羽織る。
まだ10時30分だ。お腹もすいてないので、水分とシリアルバーで済ませた。
気持ちが良いのでもう暫くぼーっと景色と風を楽しんだ。
下山は登りとは反対側に細い尾根道があり、そこを下ってから先ほどの分水嶺に出る道を行く。
暫くすると水干という場所に出る。そこは多摩川の最初の一滴が落ちるところだそうだ。
残念ながら最初の一滴は見えず、湿っていただけだ。東京湾まで138kmと書いてある。
たまたま反対側から登ってきた人たち。この水干を見に来たらしい。

緩やかな下りを暫く行くと再び先ほどの分水嶺に出る。そこから眺めが良いとのことなので西へ10分ほどで寄り道し、雁峠(がんとうげ)に出る。
少し開けた草原で、季節によっては花が咲いているみたいだ。思ったほど景色はよくない。「ぴー」と甲高い鹿の鳴き声がしたので見ると4、5頭が山の中腹を走っていた。 写真は間に合わなかった。

鹿だと思う。

再び笠取小屋まで戻り、そこから別ルートで下山していく。相変わらずクマザサが多い。
ミズナラの巨木。

昼ごはんを食べずに行動食で済ませたので予定時間よりかなり早く下山してしまった。
帰りは青梅街道を戻り、途中前回と同じく「のめこい湯」で汗を流して帰った。
今回は山梨県の山、笠取山(1953m)に行ってきた。山梨県の山ではあるが埼玉県との県境に頂上がある。西に甲武信ヶ岳、東には飛竜山から雲取山へと尾根がつながっている。
登山口までは遠いが比較的アップダウンが少なく、好展望なので初心者向けの山だ。
新座市の自宅から車で約3時間。奥多摩湖まで2時間。そこからカーブだらけの青梅街道を1時間近く走る。すれ違う車がほとんどなくなってきた頃、一之瀬林道に入るわき道から登山口に入っていく。 ちなみにこの一之瀬林道に入るところは「オイラン淵」で有名なホラースポットである。口封じのために55人の遊女が谷底へ突き落とされた悲しい場所だ。→オイラン淵
実はこの笠取山は今年の7月に登山口まで行ったにもかかわらず、登らずに帰ってきた山だ。というのも、いざ登ろうとした時に上着を忘れたのに気付き、これじゃ頂上は寒いだろうしフリースはあるけど大げさだろう、と悩み、ちょうど沖縄に大型台風が近づいていて晴れてはいるものの天候は不安定だった。上空を見ると雲が速く流れていたのでしばらく悩んだあげく中止したのだった。
ええ、根性なしです。
今回は、しっかり準備して、少し眠いけど天気もばっちり、昨年の鷹ノ巣山以来9ヶ月ぶりの登山。上着もちゃんと持った。
作場平という所から登っていく。峠に出るまではヤブ沢というルートを登る。その名のとおり、クマザサが生い茂った登山道を沢沿いに登っていく。
こんなところ。クマザサが多いので熊よけの鈴をストックに付けた。

こういう橋がいくつもかけてある。道標やベンチなど登山道はよく整備されている。

緩やかな登りが暫く続いたと思ったら1時間もしないうちにヤブ沢峠という分岐点に出る。
そこからは更に整備された登山道を行く。これまた緩やかな登り。
広葉樹いろいろ。

大して歩かぬうちに笠取小屋に着く。素泊まり用の小屋だそうだ。ちなみにここのトイレはバイオトイレが導入してある。オガクズなどと混ぜて微生物に分解させる。
しばし休憩。

緩やかな登りではあるが、シャツは汗でびっしょりだ。ザックのショルダー部分も汗でぬれている。
気温は22度だった。風は爽やかで気持ちがよい。
再び歩き始めると、だんだんと草原がまばらに見えてきて、すぐに分水嶺がある小さな丘に立つ。
この小さな丘に落ちた雨が、流れる方向によって多摩川、荒川、富士川のいづれかになる。(左下の白いのが分水嶺の印、奥の山が本日の笠取山)

分水嶺をあとにして進むにつれ奥秩父の高原風景が気持ちよい。

本日の山、笠取山の登山道。頂上まで急登だ。写真ではよくわからないが、この写真の場所から一度下ってから登りが始まる。

一番下がったところから見上げる。

ゆっくり登ればしんどくは無い。勾配がきついのでカメラを置く場所も確保できず、構図もうまくとれず、とった後またカメラのところまで戻るのが面倒なのでこんな写真しか取れなかった。

頂上。右奥に富士山。

左下の木の無いところが分水嶺から通ってきた道。

山々の名前はわからないけど、東側の景色と空。

頂上は風がとても強く、汗をかいたTシャツが冷えて寒いので急いで忘れなかったシャツを羽織る。
まだ10時30分だ。お腹もすいてないので、水分とシリアルバーで済ませた。
気持ちが良いのでもう暫くぼーっと景色と風を楽しんだ。
下山は登りとは反対側に細い尾根道があり、そこを下ってから先ほどの分水嶺に出る道を行く。
暫くすると水干という場所に出る。そこは多摩川の最初の一滴が落ちるところだそうだ。
残念ながら最初の一滴は見えず、湿っていただけだ。東京湾まで138kmと書いてある。
たまたま反対側から登ってきた人たち。この水干を見に来たらしい。

緩やかな下りを暫く行くと再び先ほどの分水嶺に出る。そこから眺めが良いとのことなので西へ10分ほどで寄り道し、雁峠(がんとうげ)に出る。
少し開けた草原で、季節によっては花が咲いているみたいだ。思ったほど景色はよくない。「ぴー」と甲高い鹿の鳴き声がしたので見ると4、5頭が山の中腹を走っていた。 写真は間に合わなかった。

鹿だと思う。

再び笠取小屋まで戻り、そこから別ルートで下山していく。相変わらずクマザサが多い。
ミズナラの巨木。

昼ごはんを食べずに行動食で済ませたので予定時間よりかなり早く下山してしまった。
帰りは青梅街道を戻り、途中前回と同じく「のめこい湯」で汗を流して帰った。